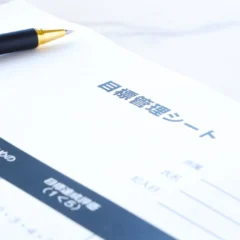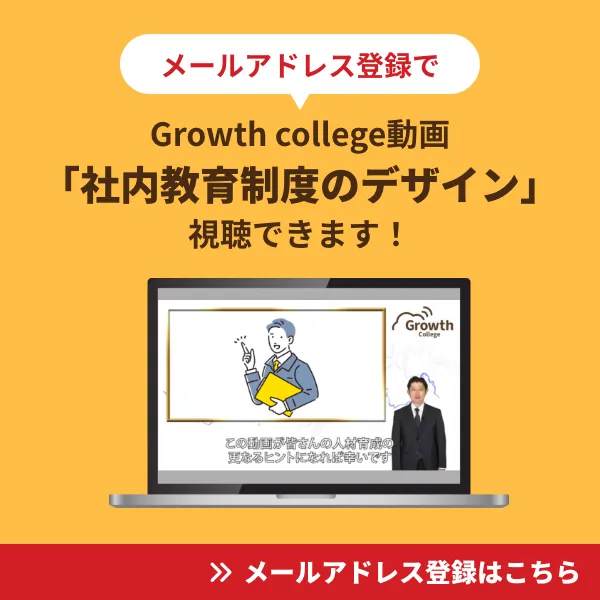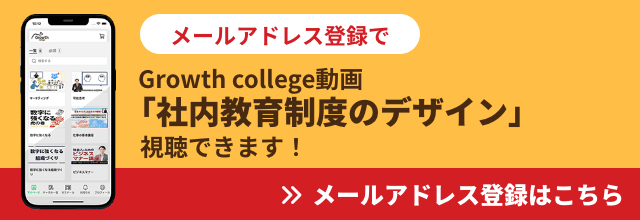企業にとって重要な「コア・コンピタンス」とは?強みを見極める方法や成功事例を解説

技術の進化、消費者ニーズの多様化、さらにはビジネスモデルの急速な変化により、企業を取り巻く経営環境はかつてないほどに複雑化・スピード化しています。こうした変化の激しい時代において、企業が生き残り、持続的に成長していくためには「自社らしさ」や独自性を明確にすることが欠かせません。
その鍵となるのが、他社には真似できない強み「コア・コンピタンス」を軸とした経営です。変化に対応しながらも、自社の本質的な価値を発揮する経営スタイルが、今ますます重要視されています。
本記事では、全国に14,000社以上の会員企業様を持ち、中小企業の経営や人材育成を長年にわたり支援してきた日創研が、コア・コンピタンスに関する基本的な知識から、その重要性、さらには実際に成果を上げた企業の事例まで、わかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧いただき、自社の経営に役立てていただければ幸いです。
目次
コア・コンピタンスとは「他社にはない自社の核となる強み」のこと
コア・コンピタンス(Core competence)とは、1990年代に経営学者によって提唱され、広く定着した経営概念の一つです。具体的には、企業が他社に対して持つ競争優位の源泉となる、中核的な能力や強みのことです。
単なる製品やサービスではなく、例えば「高度な製造技術」や「特許・ノウハウの蓄積」といった技術・製品に関する要素、また「強固なブランド力」や「グローバルな販売ネットワーク」といった要素も該当し、これらは企業の価値創出に直接つながる重要な資源とされています。
さらに、顧客企業が他社では獲得できないような顧客便益(ベネフィット)を提供し、その対価として自社の利益(プロフィット)を得る経営スタイルを「コア・コンピタンス経営」と呼びます。
ケイパビリティとの違い
コア・コンピタンスと混同されやすい概念として、「ケイパビリティ(capability)」があります。日本語では「能力」や「組織能力」と訳されることが一般的で、日創研では「組織ケイパビリティ」という表現を用いています。
ケイパビリティは、コア・コンピタンスとは異なり、より広い範囲にわたる企業の「実行力」や「仕組み」に焦点を当てた概念です。特定の事業プロセスに限定されず、企業全体を通じて発揮される組織的な能力を指す言葉で、言い換えれば、組織全体が持つ横断的な実行力や構造的な強みの総称といえるでしょう。
ちなみに、このケイパビリティはコア・コンピタンスの構成要素として位置づけられます。
ケイパビリティの具体例としては、「営業部による迅速な対応力」や「サプライチェーンの管理能力」などが挙げられます。
関連記事:ケイパビリティとコア・コンピタンスの違いを解説|企業が理解・活用することのメリットとは?
コア・コンピタンスが企業にとって重要な理由
現代のような競争の激しい市場において、企業が生き残っていくためには、他社には真似できない能力を活かすことが不可欠です。コア・コンピタンスは、まさにその競争優位の源泉となる存在です。これが明確でなかったり、存在しなかったりする企業は、容易に他社に模倣され、市場における差別化が困難になります。
多くの企業には、言語化および共有されていない隠れた強みが存在していますが、それに自ら気づいていないケースも少なくありません。
そこで、コア・コンピタンスを明確にすることによって、自社の強みを再認識でき、戦略的に活用する道が開けます。結果として、より強固な競争優位の構築が可能になるのです。
中小企業こそコア・コンピタンスが重要である
中小企業は、大企業のように人材や資本といった経営資源が豊富ではありません。そのため、市場で勝ち抜くには、「他社に負けない強み」を明確にし、それを武器とする戦略が求められます。
コア・コンピタンスが明確であれば、顧客に対して「この会社だからこそお願いしたい」と思わせる理由を提供できます。これは価格や規模ではなく、独自性に基づいた差別化の力です。
また、中小企業には、特定の地域やニッチな分野において独自の強みを持っている場合が多く見られます。こうした強みをコア・コンピタンスとして育て上げることで、顧客の獲得や事業の長期安定にもつながります。
中小企業においてこそ、コア・コンピタンスの明確化と育成が持続的成長の鍵となるのです。
コア・コンピタンスに不可欠な3つの条件

企業組織は、業界や規模を問わず、さまざまな能力(=コンピタンス)を持っています。その中で、製造や営業など事業プロセスの一部に見られる強みのうち、以下の3つの条件をすべて満たすものが、コア・コンピタンスと認識されます。
▼コア・コンピタンスの3つの条件
- 顧客に対して大きな価値を提供できること
- 競合他社が容易に真似できないこと
- 多様な市場に対して展開が可能な能力であること
次からその3つの条件について詳しく見ていきましょう。
顧客に対して大きな価値を提供できること
第一の条件は、「顧客に対して明確な価値を提供できること」です。単なる技術力や内部的な効率の良さではなく、顧客にとって「選びたくなる理由」があるかどうかが問われます。市場から見て魅力的な価値であることが、コア・コンピタンスとしての第一歩です。
競合他社が容易に真似できないこと
二つ目の条件は、競合他社が真似しづらいことです。どれほど価値があっても、簡単に他社に真似されてしまっては、競争優位は一時的なものに過ぎません。コア・コンピタンスには、長期的な差別化を可能にするだけの独自性が求められるのです。
多様な市場に対して展開が可能な能力であること
三つ目の条件は、その能力が一つの市場や製品に限定されず、複数の市場へ展開できる柔軟性を持っていることです。例えば、ある企業の基盤技術が、自動車、農業機械、発電機など異なる分野に応用できる場合、それはあらゆる市場に展開可能な能力といえるでしょう。
高い応用性があることで、将来的な成長の土台となり、長期的な競争優位を支える要素となります。
企業がコア・コンピタンスを見極める視点5つ
企業が自社のコア・コンピタンスを見極める際には、「自社の強みを洗い出す」→「強みの評価・絞り込み」といった手順が踏まれます。
その手順において「真のコア・コンピタンスであるか」を見極めるためには下記の5つ視点が重要となります。それぞれの視点について詳しく見ていきましょう。
1. 模倣可能性(Imitability)
模倣可能性とは、他社が同じ能力や技術をどれだけ簡単に真似できるかを指します。もし容易に模倣されるような能力であれば、競争優位が失われてしまい、長期的な強みとは言えません。
例えば、複数の独自技術が組み合わさっていたり、企業文化や暗黙知といった外から見えにくい要素が関わっている場合、他社による再現は困難になります。模倣が難しければ難しいほど、競争優位の持続性が高まります。
2. 移動可能性(Transferability)
移動可能性とは、ある強みが特定の製品や分野にとどまらず、他の製品や事業にも応用できるかどうかを示します。応用範囲が広い能力は、事業の多角化や新市場への展開時にも役立ちます。
例えば、精密なモーター制御技術を持つ企業が、自動車だけでなく、家庭用機器、医療機器、産業機械などにもその技術を展開できるなら「移動可能性が高い」といえます。「他の事業や製品でも活かせるか?」という問いがポイントです。
3. 代替可能性(Substitutability)
代替可能性は、他の技術や方法、あるいは他社の提供する類似品によって、同等の価値が得られてしまうかどうかを評価する視点です。代替が容易な場合、その能力は独自性に欠け、競争優位としての価値は薄れます。
一方、同じ成果が他の手段では実現しにくい場合、その能力は希少性と独自性を兼ね備えていると考えられます。例えば、独自の処理技術が他の手段によって代替されにくいのであれば、「代替可能性は低い」ということになります。
4. 希少性(Scarcity)
希少性とは、その能力や資源、ノウハウが、他の企業や市場においてどれだけ珍しく、手に入りにくいかを測る視点です。「それを持っている企業はほとんどいないか?」という問いに「YES」と答えられる場合「希少性が高い」と判断できます。
例としては、高度な職人技や特殊な素材の加工技術などが挙げられます。希少であるほど、他社との差別化がしやすくなり、競争優位につながります。
5. 耐久性(Durability)
耐久性とは、その能力が今だけでなく、5年後、10年後といった将来においても競争力を維持し続けられるかを問う視点です。一時的な流行やトレンドに依存した強みでは、継続的な競争優位にはなりません。
例えば、長年培ってきた品質や顧客との信頼関係に裏打ちされたブランド価値は、時間が経っても揺るぎにくい強みといえます。将来にわたって「変わらず価値があるか?」という視点で、耐久性の有無を判断します。
【事例】コア・コンピタンスの活用に成功した企業を紹介
企業がコア・コンピタンスを明確にし、それを戦略に組み込むことで、経営の安定や成長を実現した事例は多く存在します。
ここでは、実際にコア・コンピタンスを活かして経営成功につなげた企業の2つの事例を紹介します。いずれも、自社ならではの強みを発見・育成し、それを競争優位の源泉として活用していますので、参考としてご覧ください。
1. 「マネジメント力」をコア・コンピタンスにした事例
まず株式会社中村工務店様の事例をご紹介します。同社のコア・コンピタンスは「付加価値を向上させるマネジメント力」です。
取り組みの起点は、原価率を下げるための管理強化でした。材料費の無駄や手戻り、人件費といったコスト要因を徹底的に見直し、改善するための仕組みづくりを推進。さらに、下請け業者との密な連携や、企業としての考え方の共有を通じて、全体の意識と行動を統一していきました。
その結果、営業スタイルにも変革が起き、顧客満足の向上にもつながりました。同社のマネジメント手法は、一般的な工務店において「それは無理だ」と考えられてきた常識を覆し、他社には真似のできない仕組みとして定着しています。
2. 「人財育成力」をコア・コンピタンスにした事例
二つ目に株式会社水谷工業様の事例をご紹介します。コア・コンピタンスは「現場監督から指名される人財育成力」です。
同社はかつて先代の技術力と知見を基盤に経営を行っていましたが、先代の急逝を機に転機を迎えます。次期社長は将来を見据えた経営戦略として、「人財育成力」をコア・コンピタンスと位置づけ、経営の柱に据えました。
「助っ人稼業」という合言葉のもと、現場監督にとってなくてはならないアンカー職人を育成。納品書には表れない付加価値、つまり「現場で本当に必要とされる対応力や存在感」を武器とし、他社にはない独自の価値を提供しています。
その結果、現場からの信頼と継続的な受注を獲得し、費用面において多少高くても依頼が絶えない状態をつくり出しました。
このように、他社が重視しない領域に注力し、必要とされる力を育て上げたことが、同社の強固な競争優位となっています。「人を育てる力」が明確なコア・コンピタンスとなり、経営の根幹を支えている好例です。
企業にとってコア・コンピタンスは不可欠な存在

コア・コンピタンスとは、他社には容易に真似できない、自社特有の強みのことを指します。急速な市場変化や競争が激化する現代においては、この「自社ならではの強み」を再認識し、明確化することが企業の持続的な成長に不可欠です。単なる得意分野や成功体験にとどまらず、真に差別化できる要素を見極め、磨き上げていくことが求められます。
日創研では、こうしたコア・コンピタンスの考え方や、実際にコア・コンピタンス経営を構築・実践するための方法を学びたいと考える経営者・経営幹部の方々に向けて、「業績アップ上級コース」を開催しています。このコースでは、戦略的な視点で自社の強みを見つめ直し、経営に具体的に活かすための手法の習得が可能です。
「コア・コンピタンスを活かした経営をしたいが、何から始めてよいかわからない」「自社の強みが曖昧で見極めが難しい」といったお悩みをお持ちの場合は、ぜひご相談ください。また、上級コースを受講するには、事前に「新しい時代の業績アップ6か月セミナー」の修了が必要です。併せてご検討のうえ、日創研までお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。