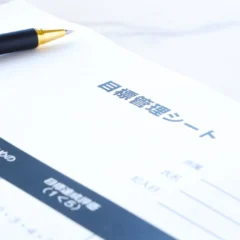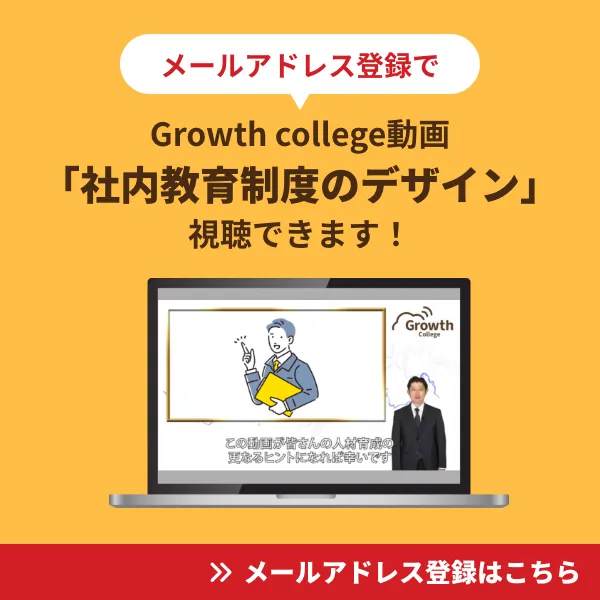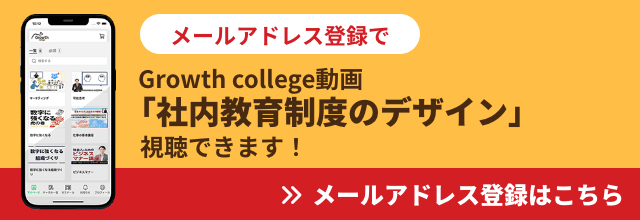コーチングとは?ビジネスにおける重要性や役割について解説

社会の変化や価値観の多様化により、現代のビジネスシーンにおいては「自ら考えて行動できる人材を育てたい」というニーズが高まっています。そこで注目を集めているのがコーチングです。
コーチングは、従来のように上司が一方的に知識やノウハウを教える方法とは異なり、双方向の対話を通じて、育成対象者の主体性や思考力を引き出していく人材育成の手法です。
本記事では、全国に14,000社以上の会員企業様を持ち、中小企業の経営支援や人材育成に長年携わってきた日創研が、コーチングの基本的な考え方と、ビジネスにおける重要性についてわかりやすく解説します。
目次
コーチングとは「相手のなかにある答えを引き出す」コミュニケーションの手法
コーチング(coaching)とは、双方向の対話を通じて、育成対象者(コーチングを受ける側)の主体性を引き出していくコミュニケーションの手法です。言い換えると、対象者自身の考えや意見を自由に語らせることに重点を置くアプローチともいえます。
コーチングを行う育成担当者(コーチングをする側・コーチ)は、相手の話をしっかりと聞いたうえで、効果的な質問を投げかけます。このやり取りを通じて、育成対象者に課題解決や目標達成に必要な「気づき」や「具体的な行動」を促していくのが特徴です。
コーチングはコーチと育成対象者の1対1で行われるケースが一般的です。ただし場合によっては、1人のコーチが複数の対象者に対応する場合や、チーム全体に向けた「コーチング型朝礼」といった形式が用いられることもあります。
ティーチングとの違い
コーチングとよく混同される言葉に「ティーチング(teaching)」があります。ティーチングとは、育成担当者が自身のノウハウや知識、課題に対する解決策などを具体的に伝える人材育成の手法です。その言葉が示すとおり「教える」「指南する」といった意味を持ちます。
コーチングとティーチングは、どちらも人材育成の手法である点は共通していますが、目的やアプローチなどに明確な違いがあります。
コーチングは、対話や質問を通じて相手の中にある答えを引き出し、長期的な成長を促す手法です。一方、ティーチングは指導者が答えを提示し、それを学習者に理解・習得させることに重きを置いています。
つまり、ティーチングは相手の考えを引き出すというより、ビジネスシーンにおいては知識やスキルを相手に伝えることが目的となります。なお、コーチングとティーチングの違いについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご参照ください。
ビジネスにおけるコーチングの重要性や取り入れるメリットとは

ビジネスの現場において、コーチングは単なるコミュニケーション手法にとどまらず、人材育成や組織づくりに大きな影響をもたらします。
では、具体的にどのような役割・メリットがあるのでしょうか。以下に詳しくご紹介します。
自分で考える人材の育成
コーチングの最大の特徴は、コーチが一方的に答えを教えるのではなく、対象者の中にある考えを引き出すという点です。コーチングを通して、対象者は受け身ではなく、自ら考えて行動できる能力が身に付きます。
また、人は質問を投げかけられることで自然と考える習慣が身につくものです。良質な質問であるほど深い思考が促され、行動の質や結果にも良い影響を与えます。反対に、曖昧で誘導的な質問は、思考の幅を狭めてしまいます。
つまり、コーチがいかに質の高い質問をし、どのように対象者と向き合うかが、その人材の成長を大きく左右するのです。
このようにして、コーチングは「指示待ち」ではなく、自分で考え行動する社員さんを育てる有効な手段となります。
仕事への意欲の向上
次に挙げられるメリットは、仕事への意欲を高められることです。
コーチングでは、傾聴や共感を大切にした対話を重視するため、育成対象者は「自分の存在が認められている」と実感しやすくなります。この感覚は、安心感や信頼につながり、結果として仕事へのモチベーションの向上や離職率の低下にもつながっていきます。
また、人は自分で考えて決断したことに対してこそ本気で取り組もうとするもの。例えば、ビジネスシーンにおいて上司が部下の意見を尊重し、自ら決断させる関わり方ができれば、その分やる気も高まり、行動への責任感も強くなります。
つまり、社員さんのやる気を引き出したいのであれば、コーチング的な関わり方が不可欠といえるでしょう。
組織内の信頼関係の構築
コーチングを継続的に行うことで、上司と部下の信頼関係を築けるというメリットもあります。
上司がコーチとなり、対話を重ねることで、部下は自分の意見が尊重されていると感じるようになります。そのような体験を重ねていけば、部下が上司に対し安心して率直な意見を述べられるようになるため、組織全体の風通しも良くなっていくでしょう。
さらに、自分の声が届く、あるいは意見が反映されると実感することで、部下はその組織に居場所を見出し、より強い帰属意識を持つようになります。こうした信頼関係の蓄積が、チーム全体の結束力の強化にも直結してくるのです。
信頼をベースにした職場環境を築くためにも、コーチングの実践が大いに役立つと理解しておきましょう。
ビジネスパフォーマンスの最大化
コーチングを導入することは、社員一人ひとりのパフォーマンスの最大化にもつながります。
その理由は、コーチングによって個人の目標と組織のビジョンが明確につながるためです。目的がはっきりすると、行動も自然と具体的になり、結果として高い成果につながりやすくなります。
また、コーチングによる定期的な振り返りや前向きなフィードバックも、行動の質を高める要因となります。上司が部下の可能性を信じ、応援する姿勢を見せることで、部下は期待に応えようとし、持っている以上の力を発揮しようとするのです。
したがって、ビジネスシーンで部下の成果を最大化したいと考える企業や管理職にとって、コーチングは有効なマネジメント手法だと言えるでしょう。
リーダーシップスタイルの進化
コーチングは、育成対象者となる部下の成長だけでなく、人材を育成する側である上司のリーダーシップスタイルの進化にもつながると考えられています。
かつて主流であった「指示・命令型」のマネジメントでは、多様な価値観を持つ人がともに働く現代のビジネスシーンにおいては対応しきれないケースも増えてきました。そこで求められるようになってきたのが、「支援・伴走型」のリーダーシップです。
もちろん、すべての状況で支援・伴走型のリーダーシップが正解というわけではありません。例えば、創業時のように迅速な判断が必要な場面においては、トップダウン型のリーダーシップが適していることもあります。
重要なのは、コーチングを含む複数のスタイルを状況に応じて柔軟に使い分けることです。そのためにも、リーダー自身がコーチングスキルを身につけることは、変化の激しい現代において求められる要素となります。
ビジネスの現場にコーチングを取り入れる際の注意点やデメリット
コーチングは部下の育成や組織の変革など、ビジネスでの活用シーンはさまざまですが、導入にあたっては次に説明するような注意点やデメリットも存在します。こちらも併せて確認しておきましょう。
効果が出るまでに時間がかかる
コーチングは、実施すればすぐに目に見える成果が出るというものではありません。成果が現れるまでには、ある程度の時間と継続的な取り組みが必要です。
特に、相手が自ら気づき、行動を変えていくためには、内面の変化を促すプロセスや、コーチとの信頼関係の構築が欠かせません。このため、短期間で成果を求めすぎると、かえって失敗につながるリスクがあります。
また、具体的な数値や目標の達成といった分かりやすい結果だけに目を向けるのではなく、表情や言葉づかい、考える姿勢といった小さな変化にも注目することが大切です。
コーチングスキルがないと十分な成果が得られない
コーチングは誰でもすぐにできるものではなく、コーチをする側が適切なスキルを身につけていないと、かえって逆効果になるおそれがあります。「問いかける」「聴く」「引き出す」といった基本的な技術が伴わなければ、コミュニケーションがうまく機能しない可能性があるためです。
例えば「正解へと誘導する質問」や「結論を急がせる聞き方」は、育成対象者の主体性を奪ってしまい、本来の目的である自発的な気づきや行動変容が得られなくなります。また、相互の信頼関係を損なう原因にもなりかねません。
そのため、コーチングを効果的に行うには、研修による知識の習得だけでなく、実践とフィードバックを繰り返しながらスキルを高める必要があります。特に部下を導く立場にある上司やリーダー層には、「聴く姿勢」や「問いの質」を磨くための継続的なトレーニングが有効です。
企業がビジネスの現場にコーチングを導入する方法
ここまで見てきたように、コーチングを企業や団体の人材育成に取り入れることで、社員さんの成長や組織の活性化を促すことができます。そこで以下からは、ビジネスの現場での具体的な導入方法として代表的な2つのアプローチをご紹介します。
社内コーチの育成をする
まず、既存の社員さん・スタッフさんに対して学習機会を提供し、ビジネス向けのコーチングスキルを習得してもらう方法があります。この方法であれば、社内の文化や企業理念、行動指針に即したコーチングが実現しやすくなるでしょう。
また、一度スキルを身につければ、社内で継続的に展開しやすく、次世代のコーチを育てる体制づくりにもつながります。
社内コーチを育てる際のポイントは、「研修を受けて終わり」ではなく、実践とフィードバックを繰り返しながらスキルを定着させること。特に本質的なコーチング力を身につけるには時間がかかるため、段階的なトレーニングプログラムの設計が重要です。たとえば半年程度の育成期間を設け、学びと実践をバランスよく取り入れると効果的です。
さらに、定期的に外部の専門家によりスキルチェックを行うことで、指導の質を保ちやすくなります。
外部コーチを依頼する
もう一つの方法は、外部からコーチングのプロを招き、幅広い階層の社員さん・スタッフさんに対しコーチングを行ってもらう形です。外部コーチは豊富な経験と知識を持っており、社内の人間関係や利害関係に左右されることなく、客観的な視点で社員さんと向き合うことができます。
特に経営層や管理職へのコーチングにおいては、外部の立場からの働きかけにより、深い気づきや行動変容が期待できるでしょう。
ただし、1対1のコーチングは単価が高くなる傾向があるため、予算とのバランスを考慮する必要があります。導入前には、費用対効果を見極めたうえで慎重に検討するとよいでしょう。
ビジネスにおいてコーチングは組織や成果に良い影響を与える

コーチングは、対話を通じて相手の主体性や成長意欲を引き出す人材育成手法です。ビジネスの現場において、自分で考えて行動する人材の育成や意欲向上、信頼関係の構築にも効果があり、組織のパフォーマンスやリーダーシップの質も高めてくれます。
ただし、効果を実感するまでにはある程度の時間とスキルが必要であり、導入方法にも工夫が求められます。社内での育成と外部活用をうまく使い分けながら、コーチングの導入を検討してみましょう。
なお、日創研では、コーチングの基本が学べるセミナー「企業内マネジメントコーチング1日セミナー」をご用意しております。
本セミナーでは、一般的な個人向けコーチングとは異なり、企業内で成果を上げるために、上司がどのように部下の成長を支援すべきかという視点で学べます。特に指示命令型のリーダーシップに偏りがちな方、自分の考えに固執しやすい傾向のある上司や経営者の方には、ぜひご参加いただきたい内容です。
また、企業内マネジメントコーチングやコーチング型朝礼大会といった内容も含む「企業内教育インストラクター養成コース(TT)」もご用意しております。
このコースでは、自社の業績を向上させるために必要な経営知識・技能を、様々な角度から講義と体験を通して習得していただけます。ぜひ「経営者に必要な教育を学びたい」「業績向上・組織活性化に直結するスキルを学びたい」という方はあわせてご検討ください。