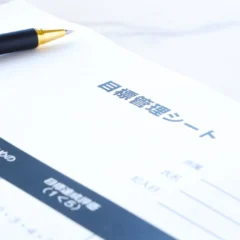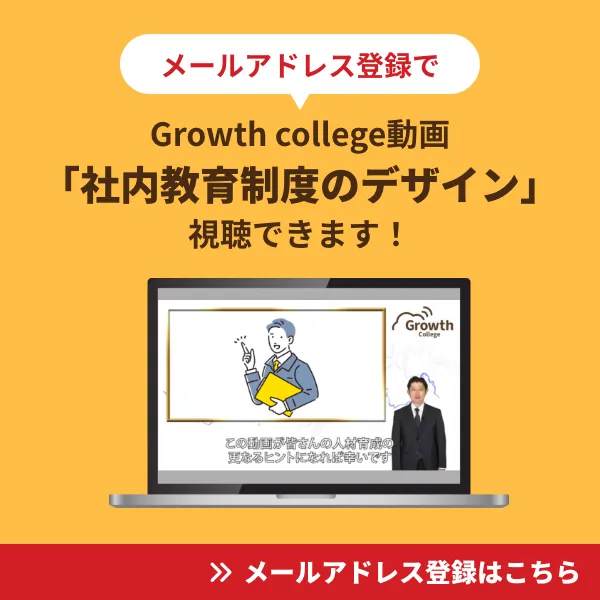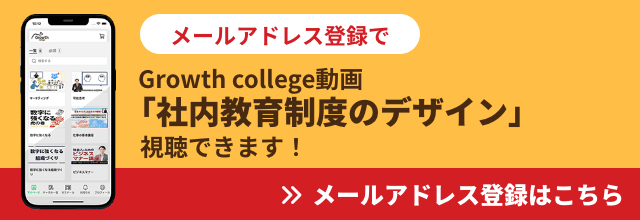コーチングのやり方はどうすれば良い?実践例を交えながら解説

人材育成や社員さんの成長支援の一環として、コーチングの導入を検討している企業もいらっしゃるかもしれません。
コーチングを実践するうえで意識したいのは、本人が自分でも気付いていない考えや可能性に自ら気付けるように導くこと。そのためには、コーチ(上司や指導者)が一方的に話すのではなく、質問や対話を通じて、本人から気付きを引き出すことがポイントとなります。
本記事では、全国で14,000社以上の会員企業様を持ち、数多くの中小企業において人材育成を支援してきた日創研が、「コーチングのやり方を知りたい」「人材育成や組織のパフォーマンス向上にコーチングを活用したい」という方に向けて、実際の質問例を交えながら、コーチングの進め方を解説します。
実践の際に押さえておきたいポイントや注意点、避けるべきNG例についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
コーチングとは?人材育成におけるコーチングの重要性
コーチングとは、問いかけを通じて相手に内省を促し、自ら気付きを得られるよう導く手法です。そのため、人材育成の場面において有効なアプローチとされています。
このコーチングを取り入れることで、以下のような効果が期待できます。
- 個人の主体的な成長を促す
- モチベーション向上
- コミュニケーションの幅が広がり、組織内の信頼関係を深める
- 変化に対応できる人材の育成 など
ティーチングとの違い
コーチングとティーチングは、いずれも人の成長や学びを支援する手法ですが、その目的やアプローチには明確な違いがあります。
コーチングは、問いかけや傾聴を通じて相手の内面に働きかけ、自らの中にある答えを引き出すことを重視し、双方向のコミュニケーションであることが特徴です。
一方で、ティーチングは知識や技術を伝えることに重きを置く手法です。学習者がまだ知らない情報を習得することを目的としており、講義や説明といった形式が中心となります。
このように、両者は目的とアプローチが異なるため、状況や相手に応じて適切に使い分けることが重要です。
【実践例】コーチングのやり方とは?質問例とあわせて解説
コーチングは、相手の内面から気付きを引き出すことを目的としているため、効果的な質問を用いながら段階的に対話を進めていくことが重要です。
ここでは、コーチングの実践的な進め方を4つのステップに分けて、具体的な質問例とともに解説します。
1. ヒアリング・現状把握
まずは、対象者が現在どのような状況にあるのかを明らかにするために、ヒアリングおよび現状把握を行います。
業務内容や感じていること、課題の背景などを「事実」として整理し、感情面も含めた共通理解を形成することがポイントです。
- 今、あなたはどのような業務に取り組んでいますか?
- 最近、うまくいっていると感じることは何ですか?
- やりにくいと感じることは何ですか?
- 困っていることや悩んでいることはありますか?
- (困っていることや悩んでいることに対して)どう感じていますか?
- なぜそのような状況になったとご自身では考えますか?
- 周囲(上司・同僚)からはどんなフィードバックを受けていますか?
2. 課題とその解決策を具体化
現状の整理ができたら、次は課題の本質に気付いてもらい、対処すべきポイントと進むべき方向性を一緒に考えるステップに進みましょう。
- 今の課題を一言で言うと、どんなことだと思いますか?
- その課題の背景や原因にはどんなものがあると思いますか?
- それを改善するには、どんな方法が考えられますか?
- 似たような状況でうまく対処できたことはありますか?その時はどうしましたか?
- 何が変われば、この問題は解決できそうですか?
3. 自身の目標と達成方法を明確化
より良い成長を目指すためには「目標設定」が不可欠です。この段階では、理想の状態を描きながら、現実的で行動につながるゴールを明確にしていきます。
- この問題が解決したら、あなたにとってどんな変化がありますか?
- 理想的な自分の姿は、どんなイメージですか?
- その理想に近づくために、どんな目標が考えられますか?
- いつまでにその目標を達成したいですか?
- どのようなスキルや行動が必要だと思いますか?
- 目標達成を妨げそうな要因には何がありますか?どう対処できますか?
4. 目標をもとに行動計画書を作成
最後に、目標達成に向けた具体的な行動を計画します。「いつ・何を・どうやって」実行するかを明らかにし、実行可能な形で管理できる状態にしておくことが成功のカギとなります。
- この目標に向けて、まず今の自分にできることは何ですか?
- 1週間以内にできる行動は何ですか?
- 誰に相談・協力を求めますか?
- 目標達成までのステップをどのように分けられますか?
- 進捗をどのように確認・振り返りますか?
- 振り返りはどのタイミングで、どのように行いますか?
コーチングを実践するうえでのポイントや注意点

効果的なコーチングを実践するためには、単に質問を投げかけるだけでなく、いくつかの重要なポイントを意識する必要があります。ここでは、特に意識したい3つの視点を解説します。
継続的に行うこと
コーチングは一度きりの面談で成果が出るものではありません。相手の変化を促し、行動の定着を目指すには、継続的なフォローが不可欠です。
定期的に時間を確保し、週に1回や月に1回などスケジュールを決めて実施することで効果を発揮します。短期的な目標や進捗状況を確認しながら、軌道修正を行いましょう。
ただし、継続するあまり内容が形骸化しないよう注意が必要です。毎回の対話で目的を明確にし、本人にとって意味のある時間となるよう心がけましょう。
信頼関係を築くこと
コーチングの効果を高めるには、対象者との間に信頼関係を築くことが前提となります。信頼があることで、相手は本音を語りやすくなり、より本質的な部分にアプローチしやすくなります。
そのためには、相手の話を否定せずに傾聴する姿勢が求められます。共感を言葉にして伝えたり、約束を確実に守ったりすることも信頼構築に有効です。
また、コーチングの内容にはプライベートな話題が含まれることもあるため、秘密保持への配慮も欠かせません。なお、指導や評価の立場が前面に出すぎると、相手が心を閉ざしてしまう恐れがあるため注意しましょう。
双方向のコミュニケーションを心がけること
コーチングは、知識を一方的に伝える「教える」行為とは本質的に異なり、対話を通じて、相手の中にある答えや可能性を引き出すことが目的です。
そのためには、オープンクエスチョンの活用が効果的です。「YES/NO」で答えられる質問ではなく、「どう思いましたか?」や「なぜそう考えましたか?」といった問いかけは、相手の思考を深める助けになります。
また、「◯◯ということですが、それはどういう意味ですか?」というように、相手の発言を繰り返して問い直すことで、さらに深い気付きにつながります。加えて、沈黙を恐れずに相手が考える時間を尊重することも大切です。
このように「教えるより引き出す」姿勢を意識しながら、双方向のコミュニケーションを重ねていくことが、良質なコーチングには欠かせません。
NGなコーチングの例
コーチングを効果的に機能させるためには、やってはいけない関わり方を理解しておくことが重要です。以下に、避けるべき代表的なNG例を紹介します。
指示ばかりする
コーチングの本質は、相手の自発的な気付きや成長を促すことにあります。しかし、コーチが常に「こうやってやって」「次はこれをして」などと細かく指示を出し続けてしまうと、相手は自分で考える力や主体性を養う機会を失ってしまいます。
その結果、「言われた通りに動くだけ」という受け身の姿勢になり、自立的な判断力や行動力が身につかず、本人の成長も限定的になってしまいます。
例えば、問題解決のための行動を決める時、「この場面ではこのように行動して、次はこうしよう」と細かく指示するのではなく、「この場面においてはどのように行動するのが良いと思う?」と問いかけることで、相手に考える機会を与えることができます。
相手の話を遮る/否定する
コーチングにおいては「傾聴」の姿勢が重要です。相手の話を最後まで聞かずに途中で遮ったり、意見を否定したりする行為は、信頼関係を損なう原因となります。
例えば、部下が自分なりの意見を伝えようとしているにもかかわらず、コーチが「いや、それは違うよ」と返してしまうと、相手は「どうせ話しても意味がない」と感じるようになり、次第に発言を控えるようになります。
こうした状況を避けるためには、相手の意見に対してすぐに判断を下すのではなく、「なるほど、そう考えたんだね。その理由をもう少し聞かせてもらえる?」といった姿勢で対話を続けることが大切です。これにより、相手は自分の考えを安心して表現できるようになります。
答えを先回りしてしまう
コーチングでは、問いかけを通じて相手自身が答えにたどり着く過程を重視します。しかし、コーチが先回りして「それなら◯◯すればいいよ」と解決策を提示してしまうと、相手の思考を深めるチャンスが奪われてしまいます。
問題解決の方法を自分で考えることは、主体的な成長を促すうえで極めて重要です。相手が課題に直面しているときこそ、「その課題を乗り越えるために、どんな選択肢があると思う?」と問いかけることで、思考力と自己解決能力を育てる支援ができます。
このように、コーチングにおいては「教えること」よりも「引き出すこと」が基本の姿勢です。自分の言動が相手の成長の妨げになっていないか、常に振り返る意識を持つことが求められます。
コーチングスキルを習得する方法
コーチングスキルを習得するためには、理論だけでなく実践を通じて学ぶことが不可欠です。ここでは、コーチングを身につけるための代表的な3つの方法をご紹介します。
それぞれに異なるメリットがあるため、学習の段階や目的に応じて選択したり、組み合わせてみたりしましょう。
プロによるコーチングを受けてみる
まず一つ目は、プロのコーチから直接コーチングを受けてみることです。自分自身がクライアントとしてコーチングを体験することで、その効果や進行のプロセスを実感しながら学ぶことができます。
どのような問いかけが行われるのか、どのようにして気付きが引き出されるのかを体感することで、「コーチングがどのように機能するのか」を具体的に理解できます。また、セッションを通じて自身の思考や視点にどのような変化が起こるのかを感じることで、コーチの技術やスタイルを肌で学ぶことも可能です。
例えば、ビジネスコーチングの専門家から月に1回のセッションを受け、そのやり取りを振り返ることで、自分自身の質問力や傾聴力の向上にもつながります。
特にこれからコーチングを学び始める初心者にとっては、「まず体験してみる」ことが、実践的な学びのスタートラインとして効果的といえるでしょう。
資格を取得する
より体系的に学びたい場合には、認定機関が提供するコーチング資格を取得するのも有効です。
資格取得の過程では、理論だけでなく実践的なトレーニングも含まれており、コーチングに必要なスキルを段階的に身につけることができます。また、資格は社内外におけるスキルの証明にもなり、説得力や信頼性を高める点でもメリットがあります。
実際に、企業の人材育成担当者やマネージャーが、リーダーシップの向上を目的として資格取得を目指すケースも増えています。キャリア開発の一環としても、十分に価値のある選択肢です。
研修・セミナーで学ぶ
もう一つの有効な方法が、コーチングに関する研修やセミナーに参加することです。社内で実施される研修や、外部の公開セミナーを活用することで、コーチングの理論と実践の基礎を効率よく学ぶことができます。
例えば、日創研の「企業内マネジメントコーチング1日セミナー」は、企業におけるマネジメントコーチングの基本的な考え方やマインドを1日で学べるセミナーです。
またコーチングセミナーによっては、ロールプレイや実践的な演習を通じて、体感的にスキルを身につけることも可能です。他の参加者のコーチングスタイルやフィードバックに触れることも、理解を深める大きな助けになります。
まずコーチングを体験してみたい方や、将来的に組織全体へコーチング文化を広めたいと考えている企業にとっても、有意義な第一歩となるでしょう。
コーチングの進め方を理解して人材育成に活用を

コーチングは、問いかけと対話を通じて相手の気付きを促し、主体的な成長を支援する手法であり、人材育成において有効な手段です。
実践するうえでは、本人が自分でも気付いていない考えや可能性に自ら気付けるように導き、段階的なステップと良質な質問を通じて目標設定から行動計画までを導くことがポイントです。信頼関係の構築や継続的な対話、双方向のコミュニケーションを意識して、コーチングを実践しましょう。
なお、日創研では経営者や管理職、リーダー向けに「企業内マネジメントコーチング6ケ月プログラム」をご用意しております。このプログラムでは、マネジメントコーチングの実践的なスキルと対人影響力の向上を図り、スタッフさんのエンゲージメントや組織成果の向上につなげます。
人材育成や組織改革にコーチングを取り入れたいとお考えの方は、ぜひ受講をご検討ください。

質問や承認などで部下の意欲や行動を引き出し、結果をつくる人材を育てる手法がコーチングです。前向きで行動的な部下を育てたい上司には必須です。