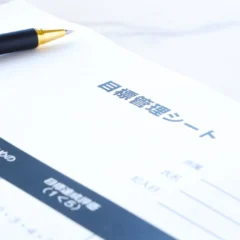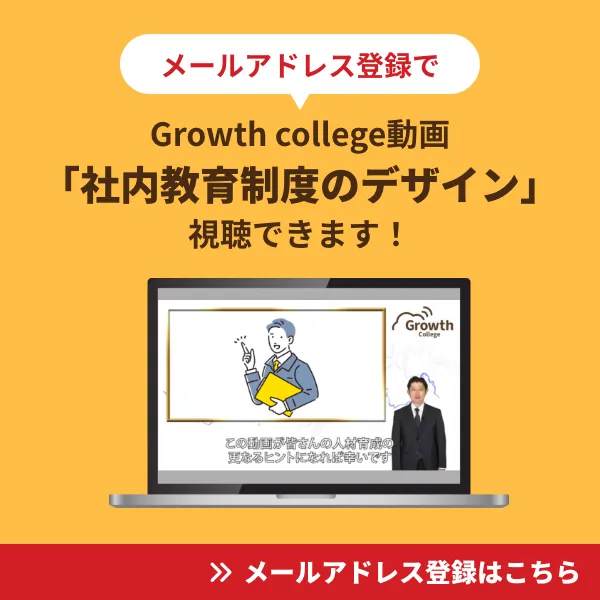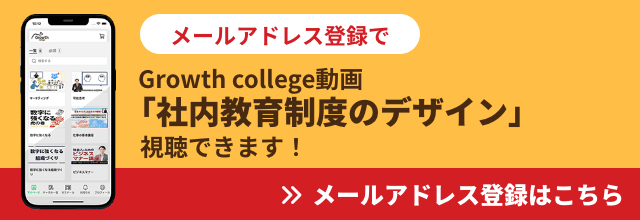コーチングとティーチングの違いとは?それぞれのメリット・デメリットと使い分けのヒントを解説

企業における人材育成の手法として、「コーチング」や「ティーチング」を取り入れているところも多く見られます。しかしながら、「コーチングとティーチングの違いがよく分からない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。どちらも人材育成を目的としたコミュニケーションの技術であるため、混同されやすいのが実情です。
そこで本記事では、全国で14,000社以上の会員企業様を持ち、数多くの中小企業の人材育成を支援してきた日創研が、コーチングとティーチングの違いについて具体的に解説します。
また、コーチングとよく混同される他のコミュニケーション手法との違いについても取り上げました。人材育成を効果的に進めるための参考として、ぜひご活用ください。
目次
コーチングとティーチングの違いとは?由来についても解説
コーチングとティーチングは、いずれも人の成長や学びを支援しますが、その目的やアプローチには明確な違いがあります。まずは、それぞれの言葉の由来から見ていきましょう。
コーチングの語源は、馬車を意味する「coach」にあります。馬車が人を目的地まで運ぶように、コーチングも相手が目標に到達するためのサポートを行うという考え方に基づいています。問いかけや傾聴を通じて、相手の内面に気づきを促すことが特徴です。
一方、ティーチングは「教える」を意味する英語「teach」に由来しており、知識や技術を相手に伝えるコミュニケーション手法を指します。情報提供や指示を通じて、相手の理解や習得を助けることが目的です。
コーチング・ティーチングどちらも似ているようで異なるものであり、どちらが優れているというものではありません。目的や育成対象者に応じて適切に使い分けることが、人材育成やマネジメントの成果を高めるうえで欠かせない視点となります。
次からそれぞれの違いについて項目ごとに深掘りしていきましょう。
目的の違い
コーチングとティーチングでは、活用する目的が異なります。
コーチングの目的は、相手の考えを引き出し、自発的な行動を促すことにあります。コーチによる問いかけ・対話で育成対象者の内側にある考え・答えを引き出し、自らの力で気づきや成長を得るよう支援するのが特徴です。
一方でティーチングは、知識やスキルを伝達し、それを学習者に習得してもらうことが目的です。指導者が答えや方法を提示し、効率よく知識をインプットさせることが重視されます。相手の考えを引き出すコーチングとは異なり、自身の考えを相手に理解してもらうことが主眼です。
対象者の違い
コーチングとティーチングは、それぞれ向いている対象者にも違いがあります。
コーチングは、すでにある程度の経験や知識を持ち、自分で考えて行動できる力がある人に適しています。自分の課題を整理し、行動に移すだけの準備ができている人材に対して、気づきを与える効果が期待できるでしょう。
一方、ティーチングは新入社員や初心者、未経験者のように、まずは基本的な知識や方法を身につける段階にある人に向いています。知らないことを一から教えるため、学習の初期段階において特に有効です。
アプローチの違い
両者の手法では、コミュニケーションの取り方にも違いが見られます。
コーチングは、問いかけや傾聴を通じて相手の「考え」を引き出す、対話・支援型のアプローチを取ります。相手に自由に話をさせ、そのなかから課題や解決策を本人に気づかせるのが基本姿勢です。例えば「どうなりたいか?」「今ある障害をどのように乗り越えるか?」といった問いを通して、自発的な行動を促します。
一方でティーチングは、知識やノウハウを一方向的に伝える説明・指導型のスタイルです。新入社員研修などでは、「電話応対のマナー」や「Excelの基本操作」などを一つずつ丁寧に教えていくといった場面が該当します。つまり、答えを伝えて相手に理解・習得させることが重視されます。
関係性の違い
コーチングとティーチングでは、関わり方や立場といった関係性における違いも特徴的です。
上司と部下の関係であっても、コーチングでは対等なパートナーとして関わり、上司は支援者として部下と共に並走します。相手を指導するというよりは、共に考えながら成長を支援する姿勢が求められます。この対等な関係性によって、信頼関係を築きやすくなるのも特徴です。
一方、ティーチングは教える側が指導者として主導権を持ち、教わる側との間に上下関係が存在します。知識を提供する側と、それを受け取る側という構図の中で進行するため、スピーディな知識伝達が可能です。
求められるスキルの違い
コーチングとティーチングでは、それぞれ実践する上で必要となるスキルも異なります。まずコーチングでは、下記のようなスキルが必要とされます。
- 傾聴する能力
- 質問する能力
- 相手の感情や意図などを正確に捉える能力
- 自身の感情をコントロールする能力
コーチングを行うには、相手の話をじっくり聞き、思考を深めるための質問ができる能力が欠かせません。コーチングに必要なスキルは、実践と振り返りを繰り返すなかで身につけていきます。
一方でティーチングにおいては、伝える力が重要です。専門的な内容を噛み砕いて分かりやすく説明したり、例え話や図解を活用しつつ、イメージしやすいように伝えたりする技術が求められます。
コーチング型朝礼に活用できる「13の徳目」の内容や人材育成におけるメリットとは?
コーチングと他のコミュニケーション手法との違い

コーチングと混同されやすい他のコミュニケーション手法には、それぞれ異なる目的やアプローチがあります。ここでは、「メンタリング」「コンサルティング」「カウンセリング」の3つについて、コーチングとの違いを交えながら解説します。
メンタリング
メンタリングは、主に若手社員の成長やキャリア形成を支援するためのコミュニケーション手法です。経験豊富な先輩社員(メンター)が、自らの体験や価値観を共有しながら、後輩(メンティ)を導いていくスタイルが特徴です。
対象となるのは、経験の浅い社員や入社間もない若手層が中心で、悩み相談や長期的な育成に有効です。例えば、メンター制度を通じて、新入社員と入社3年目の先輩社員が定期的に面談を行う場面が該当します。
メンタリングでは、相手の心理的な側面にも寄り添いながら、助言や励ましを通じて成長を支援します。自身の経験に基づいたアドバイスを積極的に伝える点が、コーチングとの違いです。
コンサルティング
コンサルティングは、専門知識を持った外部のプロフェッショナルが、企業や組織の問題に対して分析・提案を行い、解決を支援する手法です。対象者は主に経営層や事業責任者などで、経営に関する支援で用いられるケースが多く見られます。
アプローチとしては、現状の分析に基づいて改善案や戦略を「提供」するスタイルです。例えば、営業部門の生産性が低いという問題に対して、営業プロセスを診断し、具体的な改善策を提示する場面が該当します。
コーチングとの違いは、「答えを提供するかどうか」にあります。コーチングでは「答えは相手の中にある」という前提のもとで問いかけを行いますが、コンサルティングでは「専門家が答えを持っている」とされ、その答えを提供することが仕事の本質です。
カウンセリング
カウンセリングは、悩みや心理的な不調を抱える人を支援し、感情の整理や精神的な回復を目的とする手法です。主な対象者は、ストレスや不安を抱えた個人であり、職場でのメンタルケアにも活用されます。
アプローチとしては、相手の感情に寄り添いながら傾聴・受容・共感を中心に行います。悩みの解決そのものよりも、心の状態を安定させることに重きを置いているのが特徴です。
カウンセリングとコーチングの違いは、「焦点をどこに当てるか」です。コーチングは未来に向けた行動変容を重視するのに対し、カウンセリングは過去の体験や現在の感情を掘り下げ、心の整理を促します。
コーチングとティーチングのそれぞれのメリット・デメリットの違いとは
コーチングとティーチングは、目的やアプローチの違いにより、それぞれに異なるメリット・デメリットがあります。育成の目的や状況に応じて、どちらの手法が適しているかを見極めるための参考として、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
コーチングのメリット・デメリット
コーチングの最大の利点は、社員さん・スタッフさんの主体性や自律性を引き出せる点にあります。
問いかけや対話を通じて、自ら課題を発見し、解決の道筋を考えることで、自発的に行動できる人材の育成が期待されます。また、本人の内発的な動機に働きかけるため、仕事へのモチベーション向上や目標達成への意欲を高める効果も期待できます。
一方で、成果が出るまでに時間がかかる点はデメリットの一つです。相手の考える力が育つまでの過程を見守る必要があり、即効性には乏しい面があります。加えて、コーチングを実践するには高度なスキルが求められるため、コーチ側に一定の訓練や経験が必要となります。
ティーチングのメリット・デメリット
ティーチングは、相手に必要な知識やスキルが不足している場面で非常に効果的です。短時間で情報を伝達でき、複数人に対して一斉に指導できるため、効率的な教育が可能となります。また、全員が同じ方法で学ぶことで、問題に対する解決の基準や方法に共通認識を持たせやすくなります。
特に新入社員研修やマニュアル整備といった場面では、明確な答えや手順を伝えるティーチングが有効です。
しかしながら、ティーチングでは「答えを与える」ことが中心となるため、自主的な思考や行動を促すのは難しくなります。結果として、指示を待つ受け身の姿勢が定着してしまう可能性もあるでしょう。
また、教える内容は基本的に指導者自身の知識や経験に依存するため、指導者がもつ知識以上の領域については対応が難しくなるという制限もあります。
コーチングとティーチングの使い分け方の違いとは
コーチングとティーチングは、それぞれ得意とする場面が異なります。対象者の状況や指導する内容に応じた使い分けが、効果的な人材育成には欠かせません。ここでは、それぞれの手法が適している場面について解説します。
コーチングが適している場面
コーチングが有効なのは、対象者にある程度のスキルや業務経験が備わっており、自分自身で考える力がある場合です。例えば、今後のキャリアの方向性や業務改善の取り組みなど、「正解が一つではない」「本人の内面に問いかけが必要」なテーマに対して効果を発揮します。
また、緊急性は低いものの、中長期的に重要な課題や成長機会に向き合う場合にも適しています。相手の気づきや自己理解を深めることで、行動変容や意欲の向上につながりやすくなるためです。
具体例:
- 中堅社員に対して、今後のキャリアビジョンや、やりたい仕事について問いかけ、本人の内面にある目標を引き出す
- プロジェクトの進め方に悩んでいる社員さんと対話を重ね、解決策を自分で見つけられるよう支援する
ティーチングが適している場面
一方、ティーチングは対象者が業務に不慣れで、基本的な知識やスキルをまだ習得していない段階に効果的です。業務の進め方や社内ルール、企業理念など、まずは「正解を教えること」が必要な場合に適しています。
また、緊急性の高い業務や対応を間違えると大きな問題につながるような場面では、迅速かつ正確な指示が求められます。そのような場面では、ティーチングによって短時間で対応力を身につけることが重要です。
具体例:
- 新入社員に対して、自社の企業理念や業務フローを丁寧に教える
- トラブルやクレームが発生した際の対処方法やマニュアルを指導する
コーチング・ティーチングの違いを理解して適切な使い分けを

コーチングとティーチングは、いずれも人材育成において有効なコミュニケーション手法です。ただし、それぞれに目的や対象者、アプローチなどの明確な違いがあり、状況に応じた使い分けをできるかどうかが成果に直結します。
育成対象の経験やスキル、指導するテーマの緊急度や重要度によって、どちらの手法を用いるかを判断することが求められます。一方に偏るのではなく、両方を柔軟に使い分けることで、育成効果はさらに高まるでしょう。
なお、日創研では、企業内でのコーチング実践力を高めたい方に向けたセミナーをご用意しております。例えば「企業内マネジメントコーチング1日セミナー」では、部下のモチベーション向上や自主性を引き出すコーチングの基本となるマインドを体系的に学べます。コミュニケーションスタイルの幅が広がり、人材育成のポイントをつかむヒントが得られる内容です。
また、販売や接客、営業などのセールス分野でコーチングを活用したい方向けに「セールス×マーケ・コーチングプログラム(2日間)」もご用意。このプログラムでは、顧客視点を重視したマーケティング思考を養いながら、セールス現場での実践力向上を図ります。ディスカッションや対話形式のワークを通して、参加者自身の気づきと理解を深める構成となっております。
人材育成や業績向上にコーチングを取り入れたいとお考えの方は、ぜひ参加をご検討ください。