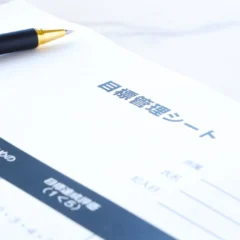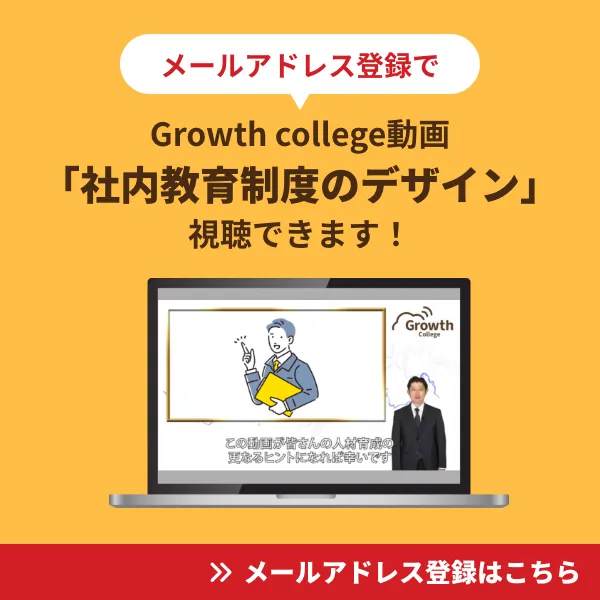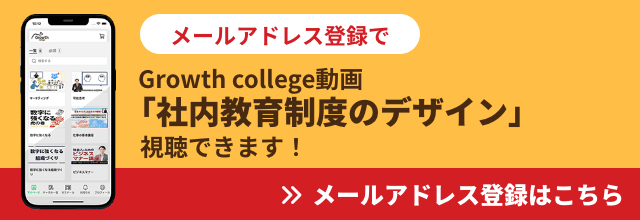コーチングの目的とは?ビジネスにおける役割や必要とされる背景

近年、人材育成やマネジメントの手法として「コーチング」が注目を集めています。多様な価値観を持つ部下への接し方や、チームの主体性を引き出す方法を模索するなかで、コーチングに関心を持つ企業が増えてきたためです。
本記事では、全国で14,000社以上の会員企業様を支援してきた日創研が、企業や組織がコーチングを導入する目的や背景を解説します。さらに、コーチングのメリット・デメリットやコーチングを取り入れても成果につながりにくいケースについてもまとめました。
コーチングの導入を検討している経営者・人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
コーチングとは?
コーチングとは、相手の可能性を最大限に引き出し、自発的な行動や成長を促すためのコミュニケーションの技術です。単なるアドバイスや指示とは異なり、質問や傾聴を通じて本人の気づきを促すことが大きな特徴です。その結果、目標達成や課題解決をより主体的に進められるようになります。
「コーチ(coach)」という言葉は、もともと「馬車」を意味します。人を目的地まで運ぶ馬車の役割になぞらえて、相手を望むところへ導くという意味で「コーチング」という概念が生まれました。
コーチングの種類は多岐にわたる
現代においてコーチングは、ビジネスの現場で幅広く活用されています。コーチングを導入することで社員の主体性が高まり、組織全体の成果にもつながるとされているためです。
また、コーチングはビジネス以外の分野でも取り入れられており、例えばスポーツの分野では選手のモチベーション向上やパフォーマンス強化、教育の分野では生徒の学習意欲を高めるために取り入れられています。
さらに、コーチングには目的や対象に応じて、さまざまな種類があります。
▼コーチングの種類(例)
- 経営者やリーダー層を対象とする「エグゼクティブコーチング」
- 人生全体に焦点を当てる「ライフコーチング」
- 将来のキャリア設計を支援する「キャリアコーチング」 など
このように、自分の課題や状況に合ったコーチングを受けることで、より効果的な成果を得ることができます。
ほかの手法との違い
コーチングと似た言葉として「ティーチング」「カウンセリング」がありますが、目的やアプローチが異なります。それぞれの違いについて項目ごとに表にまとめました。
手法コーチングティーチングカウンセリング目的相手の気づきと行動を促し、成長を支援知識やスキルを伝達心のケアや問題解決の支援アプローチ質問・傾聴・フィードバック教える・指導する傾聴・受容・心理的支援対象者成長や目標達成を望む人学習者・初心者悩みや不安を抱える人特徴相手の答えを引き出す明確な正解を伝える過去や心理的課題に焦点
| 手法 | コーチング | ティーチング | カウンセリング |
|---|---|---|---|
| 目的 | 相手の気づきと行動を促し、成長を支援 | 知識やスキルを伝達 | 心のケアや問題解決の支援 |
| アプローチ | 質問・傾聴・フィードバック | 教える・指導する | 傾聴・受容・心理的支援 |
| 対象者 | 成長や目標達成を望む人 | 学習者・初心者 | 悩みや不安を抱える人 |
| 特徴 | 相手の答えを引き出す | 明確な正解を伝える | 過去や心理的課題に焦点 |
企業がコーチングを導入・実施する目的

コーチングは人材育成において、社員一人ひとりの可能性を引き出す手法として、多くの企業が導入を進めています。次から企業や組織がコーチングを導入する目的について見ていきましょう。
個人の能力開発
コーチングは個人の潜在能力や強みを引き出し、自己成長を促す手法です。特に部下の主体性を高める効果が大きく、一方的に答えを与えられるのではなく、自ら考え行動する習慣が身につきます。その結果、学びの質が深まり、問題解決力や意思決定力が強化されていきます。
さらに、コーチ役となる上司は、質問や傾聴、承認といったスキルを習得することで、マネジメントの幅が広がることもメリットです。
このように、従来の「指示型」から「支援型」へとスタイルを転換できるため、上司と部下の双方にとって能力開発の効果が期待できるでしょう。
組織の活性化
コーチングを導入することで、組織全体における信頼関係が深まり、心理的安全性が高まります。
傾聴や承認、対話を重視する姿勢が浸透することで、上下関係を超えて意見を言いやすい風土が形成されます。その結果、チーム内での協力が促進され、多様な人材が力を発揮できる環境が整うのです。
また、会話の質が向上することで、会議の効率化や日常的な意思疎通もスムーズになります。コミュニケーションの改善によって、イノベーションや課題解決のスピードアップにつながり、組織の活性化の後押しが期待できるでしょう。
企業の業績向上
コーチングを受けると社員さんの目標達成への意識が高まり、自律的に行動できるようになるため、業務成果の向上が期待できます。さらに、変化に柔軟に対応できる人材が増えることで、競争力のある組織づくりが可能となります。
また、経営層を対象としたエグゼクティブコーチングは、経営者の意思決定力やリーダーシップの強化に効果的です。経営トップの成長は組織全体の方向性やパフォーマンスに直結するため、業績への影響も非常に大きいといえるでしょう。
離職率の低下
コーチングを導入することで、社員さんが自己成長やキャリア形成を実感できる環境が整うため、離職率の低下にもつながります。
「自分は大切にされている」「成長の機会がある」と感じられることで社員さんの働きがいやモチベーションが高まり、結果として企業への定着意識が強まるのです。
特に「働きがい」や「キャリアの展望」を重視する人材にとって、コーチングは離職防止にも有効な手段となります。
コーチングが必要とされる背景とは

コーチングが必要とされるように考えられたのにはいくつかの背景が挙げられます。
ビジネス環境が激しく変化している
市場競争の激化や技術革新、働き方の多様化によって、ビジネス環境が変化していることがコーチングが広まるようになった一つの背景として挙げられます。
従来のように、単に上からの指示を実行するだけでは成果を出すことが難しく、自ら判断し行動できる人材が組織に求められるようになりました。
主体性を持つ社員は仕事へのモチベーションも高く、組織全体の成果を押し上げます。コーチングは自律的な行動を引き出すための、時代に即した人材育成の手法といえるでしょう。
マネジメントスタイルの転換が必要である
従来のトップダウン型マネジメントは、部下の主体性を育みにくいだけでなく、時にはハラスメントのリスクを招くこともあります。現代の職場では一方的な指示ではなく、双方向のコミュニケーションが不可欠です。
コーチングは、対話を通じて本人の主体性や行動力を高める支援型アプローチであり、組織に適した新しいマネジメントスタイルとして必要とされています。
多様性に対応する必要がある
多様な人材が同じ職場で働くようになったことも一つの背景です。
グローバル化やダイバーシティの推進により、多様な価値観や文化的背景を持つ人々が同じ職場で働くことが一般的になっています。このような環境では一方向の指示ではなく、相互理解を深める「対話」が重要です。
コーチングは傾聴や質問、承認を通じて心理的安全性を高め、多様な人材が力を発揮できる環境を整えることが期待できます。異なる考え方を尊重しながら解決策を共に見いだすプロセスは、組織の持続的成長とイノベーションを支える基盤となるでしょう。
ビジネスにおけるコーチングのメリット・デメリットとは?
ビジネスの現場では、コーチングは人材育成や組織力強化に効果を発揮する一方で、導入には注意点も存在します。
ここではメリットとデメリットを整理し、コーチングを正しく活用するためのポイントを解説します。
コーチングのメリット
コーチングを導入することで、職場に多くのプラス効果が生まれます。
▼コーチングのメリット
- 部下の主体性を引き出せる
- 上司と部下の信頼関係が向上する
- 仕事に対する意欲が高まる
- 多様な意見やアイデアが出やすくなる
このように、コーチングは社員一人ひとりの自律的な行動を促し、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献します。
コーチングのデメリット
一方で、コーチングには導入する上でのいくつかの懸念点もあります。
コーチングのデメリット
- 実施には時間とコストの投資が必要
- コーチには高度なスキルが求められる
コーチには「傾聴力・質問力・承認力」といったスキルが必要です。これらを身につけるためには本や研修、セミナーなどでの学習に加えて、日常業務での実践が欠かせません。
コーチングは人と組織の成長を促す手法ですが、時間やコスト、スキルなどの条件が整っていないと逆効果になり得るため、慎重な導入が求められます。
コーチングの実施が意味ないケース
コーチングは多くの場面で効果を発揮しますが、条件が整っていない場合は期待した成果を得られません。ここでは、効果が出にくいケースとその背景について解説します。
引き出す能力や特性がない相手である
コーチングは「答えは本人の中にある」という前提で進められるため、そもそも引き出すべき能力や特性が備わっていない場合には効果が出にくいものです。
特に新入社員や経験の浅い人材は、まずティーチングによる知識やスキルの習得が優先される段階にあります。そのため、このような人材にはコーチングではなく基礎教育を中心に行い、成長の土台を築くことが重要です。
信頼関係が構築されていない
信頼関係がない状態でコーチングを行っても、相手は本音を話さず、表面的な対話にとどまってしまいます。
コーチングは安心して課題や考えを語ることが前提です。信頼がなければ「否定されるかもしれない」「評価に影響するのでは」といった警戒心が生じ、重要な気づきが得られません。
特に上司と部下の関係では、日常的なコミュニケーションの質が成果を大きく左右します。コーチングを実施する前段階においても、傾聴や承認、共感を通じて信頼を積み重ねることが不可欠です。
コーチングスキルが十分でない
コーチ役を担う人にスキルが不足していると、効果的な対話ができず、コーチングの価値が損なわれます。
コーチングでは「質問力・傾聴力・承認力」といったスキルが必要です。しかし、適切な質問ができなければ思考を深められず、傾聴力が弱ければ本音を引き出せません。さらに承認力も不十分であれば、相手のモチベーションを高めることができないでしょう。
「指導や説教に終始してしまう」「アドバイス過多になる」といった失敗を防ぐためにも、上司がコーチ役を担う場合は、体系的なトレーニングや継続的な学びが必要です。
コーチングへの理解が不足している
コーチやクライアントの双方が、コーチングの目的や進め方を誤解していると成果は出にくくなります。特に「コーチング=アドバイスをもらえるもの」というような誤認をしていると、期待とのギャップが生まれてしまいます。
さらに、組織が流行に合わせて形だけ導入すると、現場に浸透せず形骸化するリスクもあります。コーチングを導入する際は「コーチングは答えを与える場ではなく、気づきを引き出す場である」という共通理解を組織全体で持つことが重要です。
コーチング実施の流れ
実際にコーチングを実施する際は以下のような流れで進められます。
| 流れ | 詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | ヒアリング 現状把握 |
価値観や課題に対する意識を理解し、出発点を共有する 理想と現状の差分を明らかにする |
| 2 | 課題と解決策を 具体化 |
課題を明確にし、解決の方向性を一緒に探る 「何が本当の課題か?」を問いかけをする 解決策の可能性を相手自身に考えさせ、複数の選択肢を出す |
| 3 | 自身の目標と 達成方法を明確化 |
相手が主体的に取り組める目標を設定し、実行の方向性を定める 達成するための手段や必要なリソースを一緒に洗い出す |
| 4 | 目標をもとに 行動計画書を作成 |
具体的なプランを策定し、実行に移せる状態にする 「いつまでに、何を、どう実行するか」を明確に書き出す 行動ステップを小さく分解し、取り組みやすい形にする |
なお、コーチングの流れや実践例については以下の記事で解説しているので、参考にご覧ください。
コーチングを取り入れる目的を明確にして導入の検討を

コーチングは社員の主体性を育み、組織の活性化や業績向上、離職率低下などに大きな効果をもたらす手法です。一方で、信頼関係やスキル不足、理解不足があると成果につながりません。
導入にあたっては「なぜ取り入れるのか」という目的を明確にし、自社の状況に合った形で活用することが重要です。
日創研では、コーチングの基本知識やマインドについて学べる「企業内マネージメントコーチング1日セミナー」をご用意。組織で成果を上げるために上司がどのように部下の成長を支援すべきかを実践的に学べます。
さらに、より体系的に学びたい方には、経営者や幹部候補といった経営層も対象とした長期プログラムもございます。
長期的にマネジメントコーチングを習得し、組織の成長につなげたい方は、ぜひ受講をご検討の上、お気軽にご相談ください。